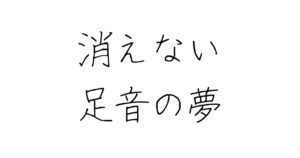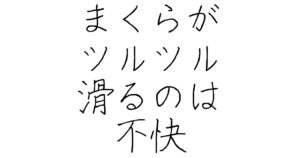古びたアパートの二階、「ゆめうら」という小さな占い部屋で、私は今日も依頼人の夢を解読している。
蛍光灯の明かりが時々チカチカとして、薄暗い部屋の隅々まで十分な光が届かない。机の上には、使い古された夢占いの本と、温めなおした回数が分からないほどになったコーヒーが置かれている。
時計が午後三時を指そうとしているとき、ドアをノックする音が響いた。
「どうぞ」
扉が開くと、二十代後半くらいの女性が恐る恐る顔を覗かせた。スーツ姿で、おそらくオフィス帰りだろう。
「あの、夢の相談に来たんですが…」
「ああ、どうぞお入りください」
彼女―川原さんは、椅子に座るなり、昨夜見た夢について話し始めた。
「私、最近毎晩同じような夢を見るんです。始まりは いつも同じで…」
川原さんの声が震えている。私は温かいお茶を出しながら、静かに頷いた。
「真夜中の図書館にいるんです。普段よく行く市立図書館なんですけど、夢の中では全然違う雰囲気で…天井が異常に高くて、本棚が空まで伸びているみたいなんです」
彼女は一息つき、お茶を一口飲んでから続けた。
「図書館の中は紫がかった光に包まれていて、空気がキラキラしているんです。それで、私が本を探していると…」
ここで川原さんは言葉を詰まらせた。
「大丈夫ですよ、ゆっくりで」
「本棚の間を歩いていると、突然、薄紫の蝶が現れるんです。それも一匹じゃなくて、たくさんの蝶が…まるで私を導くように、ある一冊の本に止まるんです」
私は眉をひそめた。蝶は変化の象徴だ。それも紫色となると、精神的な変容を示唆している可能性が高い。
「その本…手に取りましたか?」
「はい。でも、開こうとすると必ず目が覚めてしまって…」
私は目を閉じ、彼女の夢の情景を思い浮かべる。夜の図書館。紫の光。空高く伸びる本棚。そして、神秘的な蝶の群れ。
「川原さん、普段の生活で、何か決断を迫られていることはありませんか?」
彼女は驚いたように目を見開いた。
「実は…最近、婚約者と別れるかどうか悩んでいて…」
「その本は、きっとあなたの中にある答えを象徴しているんでしょう。蝶は変化と再生の象徴です。特に紫の蝶となると、精神的な進化や目覚めを意味することが…」
その時だった。突然、部屋の電気が消え、真っ暗になった。
「あ、すみません。この建物、古いので時々…」
私が立ち上がろうとした瞬間、信じられない光景を目にした。
部屋の中に、薄紫の蝶が一匹、光を放ちながら舞っているではないか。
川原さんも息を呑む。「あ…」
蝶は静かに舞い、私の机の上に置かれた古い夢占いの本に止まった。
電気が復旧した時、蝶の姿は消えていた。しかし、本は確かにそこにあった。私はためらいながらそれを手に取り、パラパラとページをめくる。
すると一枚の古い写真が滑り落ちた。それは若い女性の写真で、裏には達筆な文字で「人生に迷ったら、自分の心に正直に生きなさい ―祖母より」と書かれていた。
私はその写真を川原さんに見せた。彼女は写真を見つめ、突然涙を流し始めた。
「私のおばあちゃん…」
そう、この写真は彼女の祖母のものだった。どうしてこの本の中にあったのか、私には分からない。しかし、これは偶然ではないはずだ。
川原さんは写真を大切そうに胸に抱きながら、静かに微笑んだ。
「ありがとうございました。もう、答えは分かりました」
彼女が帰った後、私は窓の外を見つめた。夕暮れの空に、小さな紫の蝶が舞い上がっていくような気がした。
占い師として長年やってきたが、時々、現実は夢よりも不思議なことがあるものだと、しみじみと感じる瞬間だった。